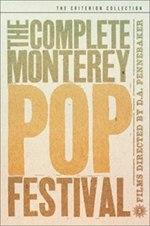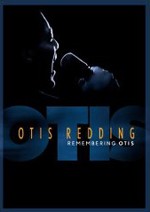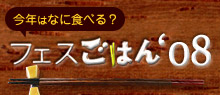DVDを見て考える… フェスティヴァルって、なになんだろう vol.2
Posted on December 3, 2008
Filed Under from ORG |
フェスティヴァルのどこに魅力があるんだろう? どこにはまっていくんだろう? そもそもフェスティヴァルってなんなのよ? と、思うことはないですか? そんなところから始まって集め出してしまったのがフェスティヴァルのDVD。それをちらりと紹介しながら、ちょっと考えてみませんか? その第二回目です。
前回紹介した『Newport Folk Festival(邦題 : ニューポート・フォーク・フェスティヴァル)[US import / 国内盤]』を見て、なにが時代を象徴していたかと考えると、間違いなく65年のボブ・ディランにつきると思います。いつの時代でも「かつての革命家は、現在の反動家になる」もの。その端的な例を見事に見せつけてくれたのがあのハプニングでした。プロテスト・ソングを歌っていた「革命家」やそれを支持していたオーディエンスがエレキ・ギターを使ったロックを「裏切り者だ」とののしっていたわけです。それはヒッピーがパンクを否定していたのに似ています。あのとき、『It’s All Over Now, Baby Blue(みんな、終わっちまった)』とディランが歌ったように、そして『The Times They Are A Changin’(時代は変わる)』と歌われたように、すでにその頃から『新しい革命』が起きていたことになります。
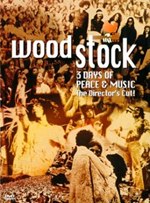 日本では、おそらく、『Woodstock(邦題 : ウッドストック 愛と平和と音楽の3日間)[US import / 国内盤]』を通してそれが伝えられたのではないかと思うのですが、実をいえば、その『新しい革命』の瞬間をとらえているのが1967年に開催された『Complete Monterey Pop Festival(邦題 : モンタレー・ポップ・フェスティバル 1967)[US import / 国内盤]』。おそらく、これこそが世界で初めてのロック・フェスティヴァルだったと思います。
日本では、おそらく、『Woodstock(邦題 : ウッドストック 愛と平和と音楽の3日間)[US import / 国内盤]』を通してそれが伝えられたのではないかと思うのですが、実をいえば、その『新しい革命』の瞬間をとらえているのが1967年に開催された『Complete Monterey Pop Festival(邦題 : モンタレー・ポップ・フェスティバル 1967)[US import / 国内盤]』。おそらく、これこそが世界で初めてのロック・フェスティヴァルだったと思います。
といっても、複雑なんですが、この『Complete Monterey Pop Festival(邦題 : モンタレー・ポップ・フェスティバル 1967)[US import / 国内盤]』は3枚組のボックス・セットという点。1枚は『Woodstock(邦題 : ウッドストック 愛と平和と音楽の3日間)[US import / 国内盤]』と同じように、映画として68年に公開された『モンタレー・ポップ』という映画で、1枚はジミ・ヘンドリックスとオーティス・レディングのライヴを収めた作品。それぞれ、単独の作品として発表されていたのを2 in 1としたもので、ジミヘンの方は『Live at Monterey(邦題 : ライヴ・アット・モンタレー)[US import / US import - Blu-Ray / 国内盤]』というタイトルで発表されていました。嬉しいのは最近再発された国内盤には未公開の映像やボーナス・トラックが入っていること。もちろん、オリジナルだけでも十二分に「衝撃」なんだけど、この再発はファンにはたまらないはずです。一方、オーティスの方は『Remembering Otis(邦題 : リメンバリング・オーティス)[US import / 国内盤]』なんですが、どうやら国内盤はすでに入手不能となっているよう。輸入盤にしても、しばらく再発はされていないようです。さらに、未発表だった2時間分の映像をまとめたのがもう1枚加えられて構成されているのが『Complete Monterey Pop Festival(邦題 : モンタレー・ポップ・フェスティバル 1967)[US import / 国内盤]』。ディープなファンにはこのあたりがたまらないんですが、さすがに高い。円高になって輸入盤がやっと8000円ぐらいの価格になっていますが、国内盤が出たときにはかなりの値段だったと思います。
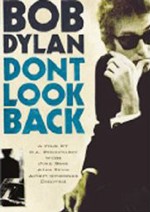 というので、なかなか簡単には見ることができないかと思いますが、まずはこの映画、『Complete Monterey Pop Festival(邦題 : モンタレー・ポップ・フェスティバル 1967)[US import / 国内盤]』にぶっ飛ばされます。この映画のサブ・チャンネルで監督、D・A・ペネベイカー(ボブ・ディランの『Don’t Look Back(邦題 : ドント・ルック・バック)[US import / 国内盤]』で有名です)とプロデューサー、ルー・アドラーの会話が聞けるのですが、これが面白い。このルー・アドラーはA&Mというレーベルの創設者のひとりで、数々の著名アーティストのマネージメントもやっています。忌野清志郎のカバーで有名なバリー・マグワイアによる『Eve of Destruction(邦題 : 明日なき世界)[US import]』も彼が手がけた仕事のひとつです。
というので、なかなか簡単には見ることができないかと思いますが、まずはこの映画、『Complete Monterey Pop Festival(邦題 : モンタレー・ポップ・フェスティバル 1967)[US import / 国内盤]』にぶっ飛ばされます。この映画のサブ・チャンネルで監督、D・A・ペネベイカー(ボブ・ディランの『Don’t Look Back(邦題 : ドント・ルック・バック)[US import / 国内盤]』で有名です)とプロデューサー、ルー・アドラーの会話が聞けるのですが、これが面白い。このルー・アドラーはA&Mというレーベルの創設者のひとりで、数々の著名アーティストのマネージメントもやっています。忌野清志郎のカバーで有名なバリー・マグワイアによる『Eve of Destruction(邦題 : 明日なき世界)[US import]』も彼が手がけた仕事のひとつです。
彼らの話を聞いているとわかるんですが、実は、もともとは当時、 『California Dreamin’(邦題 : 夢のカリフォルニア)[US import]』の大ヒットでスターとなっていたママス&パパスの大規模なライヴを開かないかという打診があったことが発端だったとか。ところが、それだけではつまらないし、もっと大きなものにしようと動き出したのがママス&パパスのジョン・フィリップス。実は、当時、急速に人気を獲得し始めていたサイモンとガーファンクルを大規模に売り出すための仕掛けでもあったという裏話もあります。(ちょうどその頃のライヴ・アルバムが『Live From New York City, 1967(邦題 : ライブ・フロム・ニューヨーク・シティ)[US import / 国内盤]』となります。)というので、ミュージシャンのジョン・フィリップス自身がさまざまなミュージシャンにコンタクトをとり、ブッキングを始めたんだそうで、わずか6〜7週間で形にしたというのが今では信じられません。
「絶対にいい演奏をしてもらいたいから、ミュージシャンには全てトップ・クラスのホテルに入れて…」
なんて発言が入っているんですが、なによりもミュージシャンに素晴らしい演奏をしてもらうために… という発想が、最近のフェスティヴァルとかなり違うような気がします。なにせ、全出演者にそんなことをしていたら、オーガナイザーは破産ですもの。
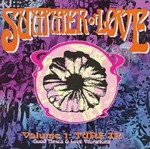 それはともかく、ロックが全国紙やマスメディアに全く取り上げられていなかったアメリカで、彼らが注目していたのがサンフランシスコ。そこで起きていたことが『Summer of Love[US import]』というアルバムなどでチェックできるんですが、そのサンフランシスコで際だった動きを見せていたプロデューサー、ビル・グレアムの協力の下に招いたのがアンダーグランドな存在だったジャニス・ジョプリンやイギリスで活動していたジミ・ヘンドリックスに、同じく、イギリスのザ・フーといった「これからのアーティスト」。ママス&パパスやサイモン&ガーファンクルといったフォークっぽい音楽が全盛だった… と思っていたのに、ふたを開けてみれば、オーディエンスを卒倒させ、歴史を変えてしまうことになったのがそういったアーティストでした。この映画、『Complete Monterey Pop Festival(邦題 : モンタレー・ポップ・フェスティバル 1967)[US import / 国内盤]』を見ているとそれが実によくわかります。そこにはプロデューサー達の思惑を遙かに超えた動きや衝撃があり、その革命をドキュメントしたのがここに詰め込まれている映像なのです。
それはともかく、ロックが全国紙やマスメディアに全く取り上げられていなかったアメリカで、彼らが注目していたのがサンフランシスコ。そこで起きていたことが『Summer of Love[US import]』というアルバムなどでチェックできるんですが、そのサンフランシスコで際だった動きを見せていたプロデューサー、ビル・グレアムの協力の下に招いたのがアンダーグランドな存在だったジャニス・ジョプリンやイギリスで活動していたジミ・ヘンドリックスに、同じく、イギリスのザ・フーといった「これからのアーティスト」。ママス&パパスやサイモン&ガーファンクルといったフォークっぽい音楽が全盛だった… と思っていたのに、ふたを開けてみれば、オーディエンスを卒倒させ、歴史を変えてしまうことになったのがそういったアーティストでした。この映画、『Complete Monterey Pop Festival(邦題 : モンタレー・ポップ・フェスティバル 1967)[US import / 国内盤]』を見ているとそれが実によくわかります。そこにはプロデューサー達の思惑を遙かに超えた動きや衝撃があり、その革命をドキュメントしたのがここに詰め込まれている映像なのです。
映画のタイトル・バックで流れてくるのはビッグ・ブラザー&ザ・ホールディング・カンパニー… というよりは、ジャニス・ジョプリンの名作アルバム、『Cheap Thrills(邦題 : チープ・スリル)[US import / 国内盤]』の巻頭に収められている曲、「Combination Of The Two(コンビネーション・オヴ・ザ・トゥー)』で、演奏風景として最初に出てくるのがスコット・マッケンジー。60年代中期のフラワー・ムーヴメントを象徴した曲で、「サンフランシスコに行くんだったら、髪に花を飾っていこう」と歌われる『San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)(邦題 : 花のサンフランシスコ)[US import / 国内盤]』が聞こえてきて、そこに続くのが、主催者でもあるママス&パパスの『California Dreamin’(邦題 : 夢のカリフォルニア)[US import]』ということで、このあたり、確かに「新しいなにか」を感じさせてくれるんですが、どこかで牧歌的な空気も感じさせます。
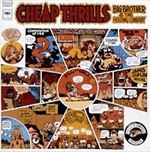 そこから、ブルース・ヴァイブを持つワイルドなバンド、キャンド・ヒート(『Very Best of Canned Heat[US import]』)、サイモン&ガーファンクルに続いて、このフェスティヴァルの翌年、バーズやポール・サイモンをゲストに大ヒット・アルバム、『Grazing in the Grass』を発表することになる南アフリカのトランペッター、ヒュー・マセケラが登場します。その後からが強力な布陣です。エリック・バードンとジ・アニマルズ(『The Best of Eric Burdon & the Animals, 1966-1968[US import]』)、ジャニス・ジョプリンとビッグ・ブラザー&ザ・ホールディング・カンパニー、ジェファーソン・エアプレイン(『Best of Jefferson Airplane[UK import]』)、ザ・フー(『The Ultimate Collection[US import]』)、カントリー・ジョー&ザ・フィッシュ(『The Life and Times of Country Joe & the Fish[US import]』)、オーティス・レディング(『Otis Blue[国内盤 / US import]』)、ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス(『Are You Experienced?[国内盤 / UK import]』)、ラヴィ・シャンカール(『At the Monterey International Pop Festival[US import]』)ということで幕なんですが、それぞれの演奏がかなりきっちりととらえられているのが嬉しいですね。
そこから、ブルース・ヴァイブを持つワイルドなバンド、キャンド・ヒート(『Very Best of Canned Heat[US import]』)、サイモン&ガーファンクルに続いて、このフェスティヴァルの翌年、バーズやポール・サイモンをゲストに大ヒット・アルバム、『Grazing in the Grass』を発表することになる南アフリカのトランペッター、ヒュー・マセケラが登場します。その後からが強力な布陣です。エリック・バードンとジ・アニマルズ(『The Best of Eric Burdon & the Animals, 1966-1968[US import]』)、ジャニス・ジョプリンとビッグ・ブラザー&ザ・ホールディング・カンパニー、ジェファーソン・エアプレイン(『Best of Jefferson Airplane[UK import]』)、ザ・フー(『The Ultimate Collection[US import]』)、カントリー・ジョー&ザ・フィッシュ(『The Life and Times of Country Joe & the Fish[US import]』)、オーティス・レディング(『Otis Blue[国内盤 / US import]』)、ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス(『Are You Experienced?[国内盤 / UK import]』)、ラヴィ・シャンカール(『At the Monterey International Pop Festival[US import]』)ということで幕なんですが、それぞれの演奏がかなりきっちりととらえられているのが嬉しいですね。
同時に、監督とプロデューサーが二人で強調しているのはジャニス、ジミヘンとオーティスが与えた異様なまでの衝撃。それは、まるで映画、『バック・トゥーザ・フーチャー』のラスト・シーン近くで、主人公がチャック・ベリーからジミヘンを想起させるギターの演奏をするシーンのようです。そこで呆然として彼を見る人たちに通じるのですが、ひょっとしてそのときの監督がモンタレーを意識していたのかもしれません。特にジミヘンがギターに火を付けて、メラメラと燃える上がるあたりのシーンで抜かれるオーディエンスの顔。「とんでもないことが目の前で起きている」ことを我々に雄弁に物語ってくれます。それに、ザ・フーのシーン。「マイ・ジェネレーション」が映画で使われているんですが、ピート・タウンゼントがギターをぶっ壊し、キース・ムーンがドラム・セットを蹴り上げるあたりが強力です。どでかい音のロックそのものが「新しかった」時代に、彼らがどれほどの衝撃を与えたか、我々の想像を遙かに超えているように思えます。
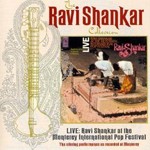 また、映画のなかで唯一2曲がフィーチャーされているのがブッカーTとMGズをバックにしたオーティス・レディング。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、この伝説のステージから半年の後、飛行機事故でこの世を去ってしまったのが、若干26歳だったオーティス。白人を中心としたロック・オーディエンスに彼が与えた衝撃が、唯一2曲をここに収めたかったという監督達の言葉からも理解することができます。さらには、その全てが終わったと想定される映画のエンディングで使われたのはシタール奏者、ラヴィ・シャンカールのインストゥルメンタル。ポップスの世界でインド音楽が受け入れられる余地など全くなかった時代に全オーディエンスを魅了し、スタンディング・オヴェーションで喝采を浴びたこの日が、どこかで新しい時代の到来を告げていたのではないかと思います。
また、映画のなかで唯一2曲がフィーチャーされているのがブッカーTとMGズをバックにしたオーティス・レディング。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、この伝説のステージから半年の後、飛行機事故でこの世を去ってしまったのが、若干26歳だったオーティス。白人を中心としたロック・オーディエンスに彼が与えた衝撃が、唯一2曲をここに収めたかったという監督達の言葉からも理解することができます。さらには、その全てが終わったと想定される映画のエンディングで使われたのはシタール奏者、ラヴィ・シャンカールのインストゥルメンタル。ポップスの世界でインド音楽が受け入れられる余地など全くなかった時代に全オーディエンスを魅了し、スタンディング・オヴェーションで喝采を浴びたこの日が、どこかで新しい時代の到来を告げていたのではないかと思います。
いろいろな意味で、この『Complete Monterey Pop Festival(邦題 : モンタレー・ポップ・フェスティバル 1967)[US import / 国内盤]』は、ぜひみなさんに見てもらいたい傑作映画だと思うし、ボックス・セットではなく、この映画『モンタレー・ポップ』の単品ででもDVD化して欲しいと切に願います。その一方で、ロック・ファンにたまらないのは、このボックス・セットに収録されている2時間にも及ぶ未発表映像。動いている姿を見たことがなかったバッファロー・スプリングフィールド(っても、ちょうどニール・ヤングが離れていたときなのが残念ですけど)から、当時のザ・バーズやジ・エレクトリック・フラッグ、アル・クーパーにローラ・ニーロのデビューといった伝説のオンパレードです。映画に顔を出していても、使われていなかった映像も嬉しい。ザ・フーの「サマータイム・ブルース」からジェファーソン・エアプレインの「サムワン・トゥ・ラヴ」にサイモンとガーファンクルの「サウンド・オヴ・サイレンス」といった名曲をあの時代に演奏していたその映像が楽しめるのです。
そういった音楽のみならず、面倒なナレーションもなく、時代を映し出しているのがまた面白い。まだまだ男性が髪を伸ばすことさえもが「新しかった」、あの時代が変化し始めているのを如実に映し出しているのです。そして、それほど多くのオーディエンスが集まってはいなかったフェスティヴァルと、その背後にある文化が爆発的な広がりを見せてしまうのが数年後。40万人を集めてしまった『Woodstock(邦題 : ウッドストック 愛と平和と音楽の3日間)[US import / 国内盤]』となっていくのです… それにしても、これは今からすでに40年以上昔の話し。ここに登場しているオーディエンスもミュージシャン達も、すでにおじいちゃん、おばぁちゃんということになります。だのに、今もこういった映像が新鮮に映るのが驚異だと思いますなぁ。
*補足情報ですが、アメリカのamazon.comでチェックすると、The Complete Monterey Pop Festival - Criterion Collectionのボックス・セットが送料込みで5500円前後。また、映画のMonterey Popも単体で購入可能のようです。なお、こちらは3500円前後。ボックス・セットがマルチ・リージョンだったので、おそらく、日本のDVDプレイヤーでも再生可能だと思いますが、現在もそうなのか、確証はありませんので悪しからず。
posted by hanasan