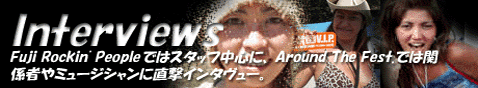
Fuji Rockin' People Vol.11
--ホワイト・ステージのPAのヘッド、東さん--Part3--
【3年間の出来事すべてが偶然やったんやろうけど、でも必然性を感じる】
97、98、99年が合わさって今のフジ・ロックのスタイルを確立させたんちゃうかな。99年だけがやったわけやない。97年に台風がなければ、98年に豊洲でやった事がなければ、どこかでフジロックフェスは失速してたんちゃうかなと思う。その3年間の出来事すべてが偶然やったんやろうけど、でも必然性を感じるのよ。というか過去にやったことに対して無駄を感じない。失敗とかそういうのを感じない。それを感じたのが俺の中では99年やったんや。
 そう、それで98、99年の忘年会の時に「日高さんな、奇跡的に終わったとか、偶然終わったとか、無理して終わったとか、それらのある種抽象的な言葉がなくなるまでやりましょう。」と言ったんや。これから10個こんな言葉があったとしたら11年目には文句言いようがなくなるやろ。フジ・ロックというのはSMASHのお祭りであって、日高さんのお祭りであってと思う。だから「そういう抽象的な言葉がなくなるまでやろう。俺ついてくよ」と日高さんに言ったんや。そうやってフジ・ロックに対しては考えていたね。まぁその間、その方向でいいのかどうかかなり迷ったけどな、やっぱり間違いなかったと思ったのは99年の苗場やったんや。
そう、それで98、99年の忘年会の時に「日高さんな、奇跡的に終わったとか、偶然終わったとか、無理して終わったとか、それらのある種抽象的な言葉がなくなるまでやりましょう。」と言ったんや。これから10個こんな言葉があったとしたら11年目には文句言いようがなくなるやろ。フジ・ロックというのはSMASHのお祭りであって、日高さんのお祭りであってと思う。だから「そういう抽象的な言葉がなくなるまでやろう。俺ついてくよ」と日高さんに言ったんや。そうやってフジ・ロックに対しては考えていたね。まぁその間、その方向でいいのかどうかかなり迷ったけどな、やっぱり間違いなかったと思ったのは99年の苗場やったんや。
【だってとにかくお客さんがホンマにみんな嬉しそうやったんからな。】
思うに日高さんがイメージしていたフジ・ロックは99年以降の話になると思うんや。97、98年は日高さんのなかで試行錯誤があったと思うな。それで00年へと移って行くわ けだけど、その年だったかな前売りが売れてなかったって聞いたんやけど、当日いっぱい来たのよ。その時小川さんが、「これはアーティストで来てないね。これは大成功なんじゃない」って言っていた事を覚えているな。確かにアーティストで来るって言う人もいるよ。そりゃしょうがない。それだけでなく、フジ・ロックというお祭りに参加してくれる人がおるっていうのも事実なんやと感じた。お客がさんがエキストラというより、お客さんが出演者になっているという感じが99年の苗場以降には感じた。そこでフジ・ロックが行事になったんやと、カリスマ性を感じる行事になったんやと思った。"だって、とにかくお客さんがホンマにみんな嬉しそうやったからな。"
けだけど、その年だったかな前売りが売れてなかったって聞いたんやけど、当日いっぱい来たのよ。その時小川さんが、「これはアーティストで来てないね。これは大成功なんじゃない」って言っていた事を覚えているな。確かにアーティストで来るって言う人もいるよ。そりゃしょうがない。それだけでなく、フジ・ロックというお祭りに参加してくれる人がおるっていうのも事実なんやと感じた。お客がさんがエキストラというより、お客さんが出演者になっているという感じが99年の苗場以降には感じた。そこでフジ・ロックが行事になったんやと、カリスマ性を感じる行事になったんやと思った。"だって、とにかくお客さんがホンマにみんな嬉しそうやったからな。"
Part4へ
Intro/Part1/2/3/4/5 reported by ORG-naoto (July 13, 2002)
|