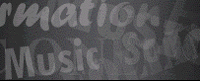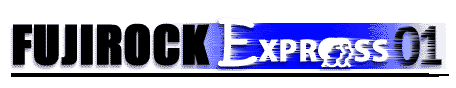
Fuji Rockin' People Vol.2 --羽仁カンタ氏--
---Fuji Rock Festivalにはいろんな分野から数多くの人たちが関わり合っています。というので、そんな人たちを紹介しようと思ってこのシリーズを始めました。誰が最初に登場するとか、そういったものは無関係です。ランダムに様々な人たちにインタヴューをして、どんどんアップしていく予定です。---- by ORG-master
海外のフェス経験した人たちがフジロックに来て必ず言うことは「世界中でこんなにきれいなフェスはない」ということらしい。そんなフジに欠かせない役割を果たしているのがA SEED JAPANである。今までフジロックに参加している皆さんには、お馴染みのことでしょう。今年は何をやるの?スタッフは何をしているの?ペットボトルはどこへ行くの?など、新宿にあるA SEED JAPANの事務所で理事の羽仁カンタさんに話を伺ってきました。長いですが、いろんな情報もあるんで、是非、最後まで読んでください。
――まず、フジロックに関わったきっかけを教えて下さい。
元々94年からレゲエ・ジャパンスプラッシュという別の野外イベントのごみのリサイクルやお客さんのマナー向上などの環境対策活動をやっていたんですよ、日高さんに97年のフジロックにステージ上で10分くらい環境問題の話をしてくれと言われて連絡があったんです。こちらとしては、単にステージ上で話をするだけじゃお客さんと近い位置にいないじゃないですか、僕としてはできれば活動させてくれと申し入れたのですが、その年は開催一週間前だったんで、次の98年の東京でやったフジロックからからごみ・ゼロナビゲーション活動というボランティアをいれてお客さんとスタッフの間に入って、お客さんの視点で来場者自身が参加者になってもらうようなの活動をやっています。
――毎年「次の年はボランティアを減らしますよ」と言っていますが、今年はボラン
ティアの数は減りますか?
2年前にやった苗場のフジロックよりお客さんも増える、特に今回は新しい人が増えるとスマッシュに言われたので、ボランティアは増やします。ボランティアは去年が178人でしたが、今年は200人。ごみ箱の数も増やして去年が14でしたが今年は19個にします。だけども入場者数に対してボランティアの比率は減っています。
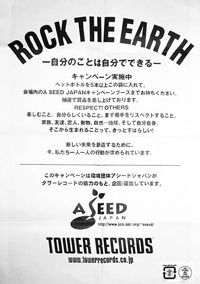 ――今年打ち出す新しい企画は?
――今年打ち出す新しい企画は?
全く新しい企画としては、会場で出るごみの半分以上は、会場で売っている飲食のごみ、発泡トレーとか紙皿とかプラスティックの器とかなんですが、これを全部紙食器に変えようとしています。全店舗では出来ないけど、ワールドレストランとあと一部で、食器を発泡スチロールの石油製品の容器からパルプなどの木材紙でなくケナフとかの非木材紙と呼ばれるものに変えます。
それからオリジナル商品を販売します。日高さんとなるべくいろんなモノに使えるようなものをぜひ一緒に作ろうという話になって、ウチでデザインしてやってみようというものです。
去年からの引き続きでは、タワーレコードと一緒にごみ袋を配っているのですが、それにペットボトル5本入れて持ってきた人に、フジロックを誇りに思ってもらうという意味で、タワーレコードのフリーペーパーの「bounce」に参加者してくれる人の名前を、1ページに1000人くらいになりますが、出します。去年までは持って来てくれた人に小物をあげていたのですが、今年は4年目にもなるし、自分で出したごみは自分で処理するのが当たり前なので、物をあげるのをやめようと思います。ペットボトル100本のリサイクルを手伝ってくれた人にTシャツプレゼントはやりま
す。
――今まで印象に残ったことや、お客さんの変化で気づいたことはありますか?
最初にビックリしたことは、今までテクノやトランスのレイヴやレゲエとかの野外イベントの活動していたのだけど、お客さん向けのごみはリサイクルするけれども、主催者やアーティストはそうは言っても別だよというのが主催者の答えでしたが、フジロックの主催者はお客さんにやらせるなら当然自分たちもやりますよ、という姿勢があって良かったです。ロックスピリッツってこういうものじゃないかと思いました。みんなが協力して作っていこう、という気持ちを作りたいというのがすごくクロスしていますね。
他のイベントの活動もやっていますが、主催者のバイブレーションというか、やっていて楽しいのはダントツにフジロックですね。ごみ箱の位置なんて我々がやることを、スタッフの人まで入ってああだこうだ話し合うし、筋さえ通っていればきちんとできるのでやりやすいです。
お客さんのマナーは年々良くなっていますね。ウチらの活動も認知されているし。驚いたのは(A SEED JAPANが参加した)初年度の98年の終わった時に「これ、ウチのボランティア!?」と思うほど、みんながごみを拾ってくれたことですね。ボランティアの活動は、帰れなくなる人もいるんで20時頃に切り上げてしまうのですが、お客さんが拾ってくれているのを見て凄いなあと思いました。
ここまで来ているので、あとはハード面の改善――食器を使い捨てじゃないものにするとか――ハード面をいじれば、ごみはもっと減らせると思います。あとは、音楽だけを聴きに来るじゃ無くてフジロックという街に遊びに来て欲しいですね。サーカスもあるし、オーガニックコーヒーも飲めるし、リサイクルをやっているし、NGOもあるし、博物館もあるし、レストラン40軒以上あるし、アーティスト目当てでなく遊びに来て欲しいという気がします。
――何かエピソード的なものはないですか?
ステージに上がって話する人って普通のお客さんの所にあんまり行かないじゃないですか。だけど、僕は結構、そこらでごみ拾ったりしているんですよ。そうすると、さっきの話は面白かったですよと声をかけてくれたり、隣に座ったお客さんからタバコ貰ったりとお客さんとの交流があることですかね。
――では、素朴な質問をいくつか。まずは、スタッフの人はライヴを観ることはでき
るのですか?
シフトで動くので、おおざっぱに言って200人ボランティがいるとすれば、100人働いて、100人休んでいます。3時間交代のシフトで自由時間があるときは観ることはできます。シフトも早番、遅番があって、早番は朝6時から17時までです。遅番は昼の12時から20時まででそれ以降は自由時間ですね。その時はスタッフTシャツを着ないで遊んでいいよと。ただ、グループで動くので自分の意見は通りません。途中抜けは出来ませんね。それと満遍なく活動をやってもらうんで、一日目グリーンステージをやったら二日目はホワイトステージとか、ステージ前のごみ箱をやったら、次は入場ゲート、その次は本部でリサイクルと全部の活動をやってもらいます。だから、グリーンステージのまん前のごみ箱になることもあるし、音も聞こえない入場ゲートの時もあるし。また、夜だけのナイトスタッフもいます。この人たちは昼間が自由時間で、夜はマーキー周辺で働きます。
説明会では特定のアーティストを観ることはできません、コンサートを観たかったら金払った方が得ですよ、と言っています。とは言ええ、きっかけ自体は音楽でOKだし、ほとんどの人は音楽好きで来るのですが、リサイクルも出来て音楽聴けて楽しいや、という感じですね。こちらも楽しんでもらえるような活動を作っています。
 ――次は乾電池のごみはどうしています?
――次は乾電池のごみはどうしています?
乾電池を集めるようなごみ箱は用意していませんが、乾電池は分別しています。スタッフに渡したり、A SEED JAPANの本部に持って来てもらえば、分別して北海道のリサイクル工場に送っています。乾電池用のBOXはあった方がいいですか?
――去年、処分に困ったことあるんで。カメラや懐中電灯なんかで乾電池を使うことが多いと思いますし。
では、検討しておきます。
――次は、あの大量のペットボトルはどこへ行くのですか?
主催者が提携しているリサイクル業者がいて、その工場に持っていって一回全部フレーク状にして再生原料のペレットというものを作ります。そのペレットをどこかの業者が買って、そこからフリースやカーペットやカセットテープの外側になったり、油化して油に戻したりします。本当はフジロックでリサイクルしたペットボトルでフジロックオリジナルフリースジャケットを作ろうよと、日高さんと話していたのですが、このペットボトルがこのフリースになるという会社が日本にはないんですよ。アメリカにはあるんですが、日本ではペレットにする会社とペレットを買う業者が別なので。日本が縦割りなのが残念ですね。
――その他のごみについては?
割り箸は王子製紙でリサイクルしています。3膳(6本)の割り箸がA4の紙になります。缶は、アルミ缶のリサイクルは日本では非常に進んでいてアルミ缶はアルミ缶になります。ガラス瓶はほとんど出ません。発泡スチロールは僕らが提携しているアムスという会社でリサイクルしてボールペンの軸になります。紙のゴミは焼却処分されます。段ボールはリサイクル出来て、また段ボールに生まれ変わったり、カードボードというピザの箱のような厚紙になります。
次のステップは洗える食器を提供することですね。ディッシュリユーズと言って、お客さんが預かり金を払って貸し出しブースから食器を借りて、食事したあと、まず、お客さん自身が紙で油分をふいてから洗って、我々が煮沸消毒します。食器を返したときにお金が戻ってくるというシステムで、メタモルフォーゼという夏に行なうテクノイベントではやりますが、フジロックは規模がデカすぎるんで難しいです。アヴァロンフィールドは水道の水圧が低いし、オアシスエリアでは下水の問題があって、インフラの整備まで出来ないということで断念しましたが、いずれは実現したいですね。
――ではフジロックが始まる前から終わるまでのスケジュールを教えて下さい。
まず、4月くらいからフジロック用のナビゲーション活動をするチームを立ち上げます。それから新しい企画は早く話を通さないといけないので、この頃から日高さんと打ち合わせします。4月の終わり頃ボランティアの募集を始めて、6月に締め切ります。6月入ってからは経費などの細かい詰めを行ないます。7月に弁当、宿泊、バスなどの人数調整をします。開催2週間前にボランティアに向けて説明会を開いて、活動自体のクオリティを落とさないのとボランティアの安全のために3時間くらい活動の説明をします。
現場にはまず、2人が火曜日に現地入りします。水曜日にさらに10人ほどが入ってごみ箱や本部のテントなどの設営をします。木曜の昼にボランティアが来て、現場の下見と日本のごみ問題のセミナーを行ないます。で、前夜祭は楽しんでもらいます。開催中、僕は12時頃寝て、3時半頃起きます。4時頃から各ごみ箱や会場の周辺を見て回ります。
――そうすると、われわれが、まだレッド・マーキーで踊っている頃には動き始めるんですね。
そういうことになりますね。最終日は1時に専用バスでボランティアは東京に帰ります。月曜はコンサートをやっていないので、ボランティでなく、アルバイトとしてスマッシュから清掃を請け負っている形になります。ボランティアの子もアルバイトとして月曜に残る人もいます。8時か9時くらいから清掃を始めて、駐車場から始まってグリーンステージの芝生に落ちているタバコを拾います。他のイベントと比べてきれいなフェスとは言っても、実際拾ってみるとタバコは多いです。20人くらい並んで一斉に人海戦術で拾っていきますが、これが結構つらいですよ。フィルターは環境に全然やさしくないんで携帯灰皿をぜひ使って欲しいです。ごみ箱の横にあるドラム缶は携帯灰皿の中身を捨てるためにあるんでよろしくお願いします。
で、火曜日にチェックして昼に帰ります。ちょうど苗場にいるのは一週間ですね。できればフジロックを1週間くらいやって、自分たちは2週間くらい居たいですね(笑)。そうすれば、みんなキャンプするだろうし、自分のことはもっと自分でやるだろうし。あと、後夜祭をやりたいですね。後片付けやった人だけ参加可能なんてね。
――フジロック以外の活動を教えて下さい。4月にやった「春風」でA SEED JAPANのブースを見たのですが。
「春風」は特別で、我々が組織的なところまで関わっていて、このグループが出来た時、自分たちがプッシュして作ったようなものなんです。他には大阪で行なわれた「舞洲フェスタ2001」。これはkiroroとかケツメイシとか出てました。それから代々木公園で行なわれた市民団体イベントの「EARTH DAY 2001」。それから7月20日には荒川で行なわれる国土交通省のイベントがあります。8月11日と12日は代々木公園でB・BOY PARKというイベント。同じ日にEquinoxというオーガナイザーが主催する武尊祭というレイヴパーティーがあります。8月18日、19日はサマーソニックとライジングサンフェスティバル。24、25、26日に原宿の商店街をきれいにしようというシンポジウムなど、9月1日2日に日本ランドでメタモルフォーゼというレイヴパーティーがあってこれで夏が終わります。
――サマーソニックはボランティアとして参加すること出来ますか?
ページをチェックしてください。B・BOYとライジングサンは募集中です。これもページをチェックしてください。
――フジに参加してサマソニに参加することも可能ですか?
可能です。いつもリピーターが3割くらいいるんですよ。残りは新規の人です。ウチらの活動はボランティアの入り口的なもので、できるだけ新規の人を採るようにしています。新規の人のほうが感動が大きいんですよ。
――ボランティアの男女・年齢比は?
女性が圧倒的に多いです。7割で、3割が男性。フジロックの班分けは10人単位で年齢・性別をバラバラにしています。力仕事もあるんで各班に男性が3〜4人は必要ですね。今年の参加年齢は高校生から最高38歳までです。大体20代前半が中心ですが18〜19歳くらいが今年は物凄く多いです。
班分けやリーダーの指名は、年功序列や男女差別をなくす意味で意図的に、たとえば社会人がいる班に大学一年生をリーダーにしたりしています。グループでボランティアの参加を申し込む人たちもいますが、内輪ネタで盛り上がるといけないのでグループを割るか、グループごとお断りすることもあります。男性の単独参加はほとんど採りますね。班ごとの連帯が強くなって、班だけで打ち上げをやるグループもあります。フジでカップルができることもあるんじゃないかな(笑)。統計取ってないんで(笑)。いろんな意味でチャンスがあるんじゃないですか。
NGO関連全般に言えることですが、女性が強いですね。入り口的なボランティアは特に女性が多いです。実際スタッフとして活動している人になると男女半々くらいになりますが。どうも男性は忙しい、男はこうあるべきだという観念がまだまだあって、参加しずらいところがあるのかもしれません。ボランティアという言葉はギリシア語の「ボランタール」という言葉からきているのですが、最初の意味は「自発性・自主性」という意味です。ボランティアという言葉には博愛とか人のための奉仕とかという誤解がありますね。
自分たちはまず、自分が好きで自分が楽しいから活動しているのであって、会社で仕事している方がよっぽど奉仕活動に見えるんですよ。サービス残業とかやってますしね。
――最後にメッセージをどうぞ。
「楽しく頑張りましょう」(スタッフの方)。「よろしくお願いします」(スタッフの方)。「日常生活では他人に依存していますが、自立してみるいいチャンスです。それと同じ空間を共有している感覚を味わってください」(羽仁さん)。
Reported by ORG-nob (July 17 2001)
|