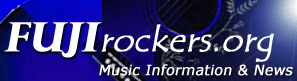Around the Fest.4
ミュージシャンやマネージャー、メディア関係の人たち等々、フジ・ロック周辺にはいろんな人たちが顔を覗かせています。というので、始めたのがAround The Fest.というシリーズ。いろんな人たちに登場してもらってフジ・ロックをいろんな角度から見てみようと思っています。
今回ご登場願ったのは、毎回オフィシャル写真家としてFRFを手伝ってくれている写真家の井上ジェイさん。昨年は、なんとorgのFuji Rock Expressも無償で手伝ってくれて、毎日遅くまで仕事をしてくれました。このサイトをチェックしている人も彼の写真はどこかで見たことがあると思います。

面白いのは、井上ジェイさんは写真家であると同時に、大のビートルズ・ファンで、レゲエ・ファン。しかも、ギターも巧い。というので、彼は原宿でレコードやさんもやっています。基本的にはジャマイカから直輸入した45が中心ですが、UKロック系の中古版も扱っていて、通なロック、レゲエ・ファンにはかなりの人気。特にレゲエのDJにとってここはミーティング・ポイントのようになっています。
そのあたりはhtpp://www.45music.comに遊びに行ってくれれば、わかると思いますよ。
 さらに、旅行代理店もやっていて、得意はイギリスを中心としたロック系イヴェントへのツアー。ヨーロッパ最大のロック・フェスティヴァル、グラストンバリー・フェスティヴァルのツアー企画に関しては最も歴史が長く、彼を通じてグラストンバリーを体験した人もかなりの数になっています。それにオアシスなどのロック・バンドの大規模なライヴなんかへのツアーも企画しています。
さらに、旅行代理店もやっていて、得意はイギリスを中心としたロック系イヴェントへのツアー。ヨーロッパ最大のロック・フェスティヴァル、グラストンバリー・フェスティヴァルのツアー企画に関しては最も歴史が長く、彼を通じてグラストンバリーを体験した人もかなりの数になっています。それにオアシスなどのロック・バンドの大規模なライヴなんかへのツアーも企画しています。
また、ジャマイカなどのカリブ海からインドを中心としたアジア系も得意で、安いフライト・チケットの手配も親切に、丁寧にやってくれるというので旅行通にも人気。数多くのミュージシャンの招聘や渡航に関しても力を入れていて、音楽からメディア業界では人気の代理店です。ご関心のある方はwww.oasis-office.co.jp/tour/に飛んでチェックしてみてください。
というので、今回のインタヴューを担当してくれたのはORG-nob。じっくり読んであげてください。
Reported by ORG-master (May 1, 2002)
-----------
フジロックの基本的なアイディアがグラストンバリーフェスティバルの影響にあるのだけれど、まだまだ日本にいると遠い存在だったりする。1984年から毎年、ツアーを主催してグラストンバリーに行っている井上ジェイさんに話を伺った。イギリスと日本の違い、グラストンバリーとイギリス国内のフェスとの比較などなかなか興味深かった。もし、お金と時間が許せば、グラストンバリーにも行ってみてはどうでしょうか?
【ツアーを始めたころ】
 ジェイさんが初めてグラストンバリーに行ったのは1984年。82年からグラストンバリーを体験していた音楽ジャーナリスト、花房浩一氏がジェイさんのいた旅行会社を訪ねたのがきっかけであった。
ジェイさんが初めてグラストンバリーに行ったのは1984年。82年からグラストンバリーを体験していた音楽ジャーナリスト、花房浩一氏がジェイさんのいた旅行会社を訪ねたのがきっかけであった。
「ボクが前の会社にいた時に『ツアーをやりたいんで企画してくれ』って来たんですよ。ジャマイカでレゲエサンプスラッシュを観に行こう、というツアーをやっていたんで音楽に精通している旅行社だと思ったんでしょう」
当時のグラストンバリーフェスティバルはCND(Campaign for Nuclear Disarmament=核廃絶運動)という団体と一緒になって、フェスの収益金をその団体に寄付していた。
「普通の旅行社だったらなかなか難しいじゃないですか。反核運動のイベントにツアー組むなんて。ボクらは身軽だったし、十分共感できたんで引き受けたんですよ」
その時に出ていたのは、エルヴィス・コステロやスミスやイアン・デューリー、フェアポートコンベンション、ジョーン・バエズ(60年代の反戦フォークの人)などだった。
「毎年毎年ハンパじゃないすごい人が出るわけでしょ、毎年見ていると何年に誰が出たか覚えてられないんだよね(笑)」
ジェイさんはフェアポートコンベンションにえらく感激したそうだ。
 「こんなアーティストも出るんだって。当時から(出演アーティストは)幅広いですからね。ツアーの始めたころの参加者はあがた森魚さんや、浜田省吾さんのところの会社の社長さんとか業界関係者が多かったです。90年代に入ってからですね。オアシスやブラーのブリットポップ系が出るようになって日本でも知られるようになったのは。それまではツアー組んでもせいぜい10人集まるのがやっとで」
「こんなアーティストも出るんだって。当時から(出演アーティストは)幅広いですからね。ツアーの始めたころの参加者はあがた森魚さんや、浜田省吾さんのところの会社の社長さんとか業界関係者が多かったです。90年代に入ってからですね。オアシスやブラーのブリットポップ系が出るようになって日本でも知られるようになったのは。それまではツアー組んでもせいぜい10人集まるのがやっとで」
「花房さんが『宝島』(当時はロックなどのサブカルチャーを取り上げる雑誌だった)とかに取材記事を一生懸命書いていたよ。あと堅い新聞や雑誌にも書いていたと思う」 日高さんがグラストンに行くようになったのは80年代半ば頃から。
「ボクらがバックステージの焚き火を囲みながら『こんなのを日本でも出来たらいいね』っていう話をしていた」
【グラストンバリーフェスティバルとは?】
 グラストンバリーの会場はマイケル・イーヴィスという人の持つ農場で、田舎で不便なところにあり、周りにあまり宿泊施設がなく、ほとんどの人がキャンプをする。イギリスの子供たちは夏になるとキャンプをするのが習慣になっていて、ボーイスカウトの発祥の地でもあるし、キャンプに対する抵抗感がないらしい。ここに10万人近くの人たちが集まると小さな都市のようで、見渡す限りのテントは壮観なんだそうだ。
グラストンバリーの会場はマイケル・イーヴィスという人の持つ農場で、田舎で不便なところにあり、周りにあまり宿泊施設がなく、ほとんどの人がキャンプをする。イギリスの子供たちは夏になるとキャンプをするのが習慣になっていて、ボーイスカウトの発祥の地でもあるし、キャンプに対する抵抗感がないらしい。ここに10万人近くの人たちが集まると小さな都市のようで、見渡す限りのテントは壮観なんだそうだ。
この町はアーサー王の伝説で有名なところで、イギリスの人なら誰でも知っている。日本で言えば、出雲とかそういうところになるかな? フェス自体は80年代にCNDの運動と一緒になることで全国規模に知名度を上げたらしい。現在では社会的な要素が薄れているけど、収益は毎回、自然保護などの団体に寄付されているそうだ。
そもそもグラストンバリーフェスティバルが始まったのは70年。ウッドストックに影響を受けてイギリスでもロックフェスが行なわれるようになり、70年の夏の前のころにバースというところで開催されたフェスを観たマイケル・イーヴィスは自分もやろうと思いついたらしい。しかも、その年の秋に1回目を始めてしまった。1回目の出演者はT-Rex(!)などで2000人弱くらいの規模だったとのこと。年々規模が拡大して84年当時で8万人限定でチケットを売っていたけど、今では、先述の通り10万人くらいは来ているらしい。
それから14歳以下は無料。しかし、やっぱりすごいのは、自分の土地を10万人に解放できるっていうこと。日本にもロックが好きで10万人がキャンプできる広さを持つ地主っていないものですかねえ。
「グラスト(英語ではこれが短縮形。日本ではグラストンと呼んでいる人が多いけど)とフジとの違いは、マイケル・イーヴィスさんが持つ自分の土地でやっているのと、自分の国のアーティストが多いので、出演料とかバンドの旅費などの経費がかかってないことですね。アーティストもいい宣伝の場になるんで出たがるんですよ」

【自分で楽しみを見つけるフェスティバル】
グラストンバリーフェスティバルが年とともに変化してきたのだろうか。
「変わってきてないですね。グラストは年齢も幅広いし、いろんな人が来るし、誰が来ても楽しめるイベントだから」
サーカスとか映画とかダンステントもあるし子供向けの施設もあるし、ヒーリングスペースとか瞑想している人がたまっているスペースがあったりもする。
「大体そういうところ行くと不思議とみんなヌードだったりするんだよね(笑)。瞑想とヌードどう結び付けていいのか分からないけど」
それから、いろんなワークショップがあって農作物の作り方とか編物とかの教室もある。要はイギリスの人たちは、ずっとステージに張り付いてないで、自分の観たいものだけを観るので、それ以外の時間の過ごし方をどう楽しもうかと考えると自ずといろんなものが出来てしまうのだそうだ。
 グラストは公式に出演アーティストの発表は一切せず、参加者は当日のプログラムで誰がいつどこのステージに出るのか知るらしい。もちろん、アーティスト側が事前に出るよと言ったりはするらしいけど。
グラストは公式に出演アーティストの発表は一切せず、参加者は当日のプログラムで誰がいつどこのステージに出るのか知るらしい。もちろん、アーティスト側が事前に出るよと言ったりはするらしいけど。
「プログラムに載っていてもいろんな都合で出ないこともある。そういうのがあっても文句はあまり言わない。参加者も心得たもので、日本みたいにガチガチに誰が出たとか出ない、とかはないみたい。誰かのコンサートでなく、イベントなんだから誰が出たって楽しもうということですね。そこに来る10万人はマイケル・イーヴィスのお客さんなわけですよ。自分の所にテント持参で泊まってもらって楽しみを共有しましょうということで、そこで過ごすための楽しみは自分で考えましょうということだから」
「自炊する人は少ないですね。食べるところがいっぱいあるから。日本と比べ、食べ物としては量はあるけど、あんまり旨くないです。フィッシュ&チップスのフィッシュは生モノなんで無い代わりに、ソーセージ&チップスだったりします。普通のサラリーマンみたいな人が家庭で作っているような料理もある。こういう人も楽しみながら参加している感じですね」
「ミュージシャンも観客の中に入って飯食ったりステージ観ていたりします。向こうの人たちは、サインくらいは求めたりもするけど、あんまり囲んだり追っかけたりしないです。プライベートは邪魔しないっていうマナーがありますね」
【他のUKのフェスティバルは】
 UKの他のイベントはプロモーターがいてビジネスでやっている。レディングやV2002が行なわれるし、ワイト島フェスティバルも復活する。
UKの他のイベントはプロモーターがいてビジネスでやっている。レディングやV2002が行なわれるし、ワイト島フェスティバルも復活する。
「V2002はヴァージングループが主催しているんですよ。ヴァージングループは音楽だけでなく、携帯電話やラジオ、飛行機、コーラなんかの他にヴァージンの電車も走っています」
スコットランドでT in The Parkというスコットランド版のグラストのようなキャンプ主体のフェスもある。イギリスはフェスティバルが流行っていて、それぞれ頑張っているようだ。
「グラストとレディングのお客さんの違いはなくて、どちらも行く人が多いです。ただ、レディングはロンドンから手ぶらで行けて、ロンドンの人たちのイベントであるけど、グラストはイギリス国内はもとよりヨーロッパ中からお客さんが集まる。でも、レディングにもキャンプ場があるんですよ」
【もっとキャンプをしよう】
1回目のフジロックはカメラマンとして参加した。
「割と客観的にスタッフ側もお客さんの側も見ていたけど、やっぱり不慣れなんでスタッフにも不備があったし、お客さんはもっと準備が足りてないっていうか。事前の宣伝が足りなかったと思う。夜は寒いですよとか、雨に対してとか」
でも、今ではグラストとフジの差はどんどん縮まってきて、あまり差がなくなってきたとのことだ。ただ、キャンプに対しての考え方が違う。
「イギリスではキャンプは子供の頃からの自然なことだけど、日本でアウトドアというとファッションになってしまう。『B-PAL』読んでいる人が音楽が好きとも限らないし」
また、ジェイさんはフジロックは10万人くらい来てもいい内容だと語る。
「フジロックでもっと多くの人たちに楽しんでもらうには、キャンプすることを啓蒙することが先決かなと思う。音楽雑誌もキャンプの仕方の記事が載ればいいのにと思う。イギリスもみんながキャンプに慣れている人ばかりではないから、音楽誌や情報誌も特集組むんですよ。テントの建て方とか服装はこうだよ、とかね。webでもやったらどうですか?」
 【こんな人に出て欲しい】
【こんな人に出て欲しい】
フジロックに対しての意見は「(外国勢を連れてくるのに)無理しなくていいと思う。もっと日本のバンドが出てもいいと思う。ボクらは洋楽ファンだけども、もっと幅広く、日本で売れている人も出ていいんじゃないかと思う。グラストもデヴィッド・ボウイとかセレブっぽい人は出ているし。自分の好きじゃない人が出たら、別のステージに行くなり、サーカス観るなりすればいい」
確かに、会社の上司を説得するのに知らないアーティストの名前を挙げるよりは、みんなが知っている人の方がいいし、認知度が上がって、みんなに支持されるフェスになれば運営しやすくなる面もあるだろう(筆者注:80年代のグラストは保守党の議員によって何度か開催中止の圧力がかけられていた。音楽マニアだけでない普通の人の支持があったから続けて来れたという面もあると思う)
「それと苗場という場所は考え直したほうがいいと思う。場所は重要ですね」
フジロックで良かったアーティストは「ニール・ヤングは観たことがなかったので、それが観れたのが去年は大収穫だった。それとレイ・デイヴィスが出てきたのにはビックリした。本当はもっと子連れの人が来てくれるような人を増やせばいいと思う。あと去年のサーカスは良かった。あれは観なくちゃ損だね。サーカスは事前の宣伝が足りなかったかな。観たいアーティストはポール・マッカートニーとかになっちゃうかな。それとXTC。メンバーは2人だけになったけど、ちゃんとしたサポートメンバーを連れてくればいいと思う」
長年フェスを観ているジェイさんは「後に大物になったアーティストの駆け出しの時代」を見ているはずなんで聞いてみると
「オーシャンカラーシーンまだ一枚目のアルバムのときで、92年にグラストのメインステージに出ていた。デビューしたときから期待されていたバンドだけど、むちゃくちゃ下手だったね。ステージが終わって、汗だくになってすごい緊張していたのが観ていても分かったくらい。で、一回消えて復活してきたらいいバンドになっていた。今みたいな実力派のバンドになるとは思わなかった。オアシスが94年に出たときもむちゃくちゃ素人だった。着ているものは普通のものだったし。だけど、オアシスも当時から名前が先行していて、すでに日本からも追っかけの女の子が来ていた」
----------------------
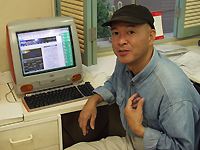 最後にメッセージを
最後にメッセージを
「フジロックはアーティストの量としては満足していて、十分イカしたイベントだと思う。もっと多くの人に注目されてほしい。やっぱりもっと宣伝してほしい。ボクも協力したいと思っている」
それからオアシスツアーの宣伝を
「ウチはグラストンバリーやレディングなどにツアー組んでいるんで、是非参加して欲しいですね。イギリスのフェスティバルだけでなく、オアシスのフィンズベリーパークのライヴとか、いろんなライヴを随時手配しています。イギリスに行く人がいればスケジュールをチェックして欲しい」
何故、イギリスでのライヴかと言えば
「イギリスのバンドはイギリスで観るのが一番だと思う。地元でやるライヴは全然雰
囲気が違うので是非体験して欲しい」
ということです。まずはHPを覗いてみてはいか
が?
reported by ORG-nob> (April, 2002)
|